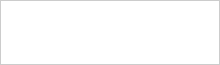私の母は70歳を過ぎてから一人暮らしを始めました。父が他界してから、実家で一人で過ごすことを選んだのです。最初は心配でしたが、母は「自分の生活は自分で守りたい」と強く主張しました。そんな母が最近、クラウド型エンディングノートを始めたと言い出したのです。
きっかけは、同じマンションに住む友人から勧められたことでした。従来の紙のエンディングノートとは違い、スマートフォンやパソコンから簡単にアクセスできて、情報を随時更新できるというのです。最初は「デジタルは苦手」と尻込みしていた母でしたが、友人と一緒に使い始めてみると、意外にも楽しんでいる様子でした。
特に母が気に入ったのは、日々の安否確認機能でした。毎朝、アプリから「今日も元気です」というボタンを押すだけで、私たち家族に自動で通知が届きます。母は「毎日子供たちに連絡するのは申し訳ないと思っていたけど、これなら気軽にできる」と喜んでいました。確かに、以前は週に一度の電話で安否確認をしていましたが、今では毎日母の元気な様子がわかり、私たち子供も安心できています。
ある日、母から驚きの報告がありました。「銀行のパスワードや、保険の契約書の保管場所も全部記録できるのよ」と。実は、父が他界した際、重要書類の探索に苦労した経験があったのです。母は「あの時のように、子供たちに迷惑をかけたくない」と、クラウド型エンディングノートに様々な情報を入力し始めました。
保険証書の保管場所、銀行口座の情報、各種会員証の番号、そしてスマートフォンのロック解除パスワードまで。母は「これで安心」と満足そうでした。もちろん、セキュリティ面も万全で、情報は暗号化されて保管されているため、指定した家族以外はアクセスできません。
特に印象的だったのは、母が「思い出の整理」を始めたことです。家族旅行の写真をスキャンしてアップロードしたり、思い出の品々の由来を記録したり。「これは、あなたが小学校の時に作ってくれた陶器よ」「この着物は、おばあちゃんの形見分けよ」といった情報を、一つ一つ丁寧に入力していました。
また、母は医療情報も記録しています。普段服用している薬の情報や、かかりつけ医の連絡先、アレルギー歴なども全て入力されています。「万が一の時に、救急隊員や医療機関に正確な情報を伝えられる」と、母は安心していました。
さらに、母の生活ぶりに変化が現れました。毎日の安否確認がルーティンとなり、生活リズムが整ってきたのです。友人たちとLINEでメッセージを交換する機会も増え、デジタル機器への抵抗感も薄れていきました。
ある日、母が「私からのメッセージ」という機能を使って、将来の私たちへ向けたビデオメッセージを録画したと教えてくれました。「いつか見てほしい」と言って、それ以上は教えてくれませんでしたが、母らしい温かいメッセージが残されているのだろうと思うと、胸が熱くなりました。
クラウド型エンディングノートは、単なる情報管理ツールを超えて、家族の絆を深めるきっかけとなりました。母は「これがあることで、子供たちに余計な心配をかけずに済む」と話します。確かに、以前より母との会話が増え、日々の暮らしぶりがよく分かるようになりました。
最近では、母の友人たちの間でも使い始める人が増えているそうです。「みんなで使っていると、お互いの安否確認もできるし、心強いわ」と母。一人暮らしの高齢者同士で支え合うコミュニティも自然と形成されているようです。
私たち子供世代にとっても、母の情報がデジタルで整理されていることは、大きな安心につながっています。緊急時の連絡先や医療情報がすぐに確認できること、重要書類の保管場所が明確になっていることは、とても心強いものです。
母は最近、「このシステムがあることで、自分の人生を整理する良いきっかけになった」と話してくれました。確かに、思い出の品々を整理しながら、その由来を記録する作業は、自分の人生を振り返る良い機会になったようです。
クラウド型エンディングノートは、デジタル時代における新しい形の「親孝行」かもしれません。離れて暮らす家族の絆を深め、お互いの安心を紡ぐツールとして、その価値は計り知れません。母が教えてくれた、この新しい形の家族のつながり方は、きっと多くの人の心に響くのではないでしょうか。
今では、私も将来に向けて自分のエンディングノートを始めようと考えています。大切な情報を整理し、家族に伝えたい思いを記録する。それは、次の世代へのバトンを渡す、新しい形の遺産相続なのかもしれません。